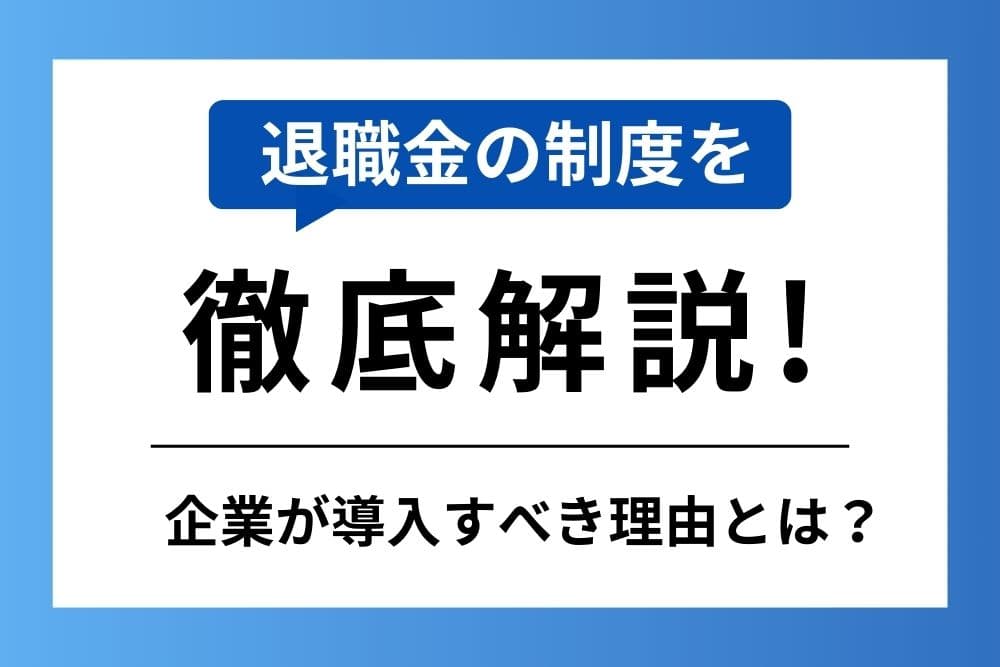お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
中小企業の退職金制度を解説!中退共などは活用すべきなのか?
 詳細を見る
詳細を見る
中小企業でも退職金制度を整備すべき理由
中小企業でも導入できる退職金制度
中小企業の多くが導入する中退共とは?
中小企業が活用する中退共の制度概要
中小企業が中退共を活用した際の退職金額
中小企業の経営者・人事担当者にとって、人材の定着率向上や採用競争力強化は重要です。退職金制度を導入することで従業員の長期勤続を促し、会社へのエンゲージメント向上といった効果が見込めます。
本記事では、中小企業における退職金制度の必要性を詳しく解説し、具体的な制度として多くの企業が活用する中小企業退職金共済(中退共)の特徴や導入方法について紹介します。
退職金制度を導入するメリットや、中退共を活用した場合の退職金モデルケースも取り上げますので、自社の人材戦略にぜひお役立てください。
とはいえ、中小企業を含めほとんどの企業で用意されている退職金制度だけでは従業員の豊かな老後を支えるほどではありません。
もし、退職金制度を構築しながらより充実した老後への対策を企業側が用意するのであれば、当社インプレームのマネーリペアも検討してみてください。
目次
中小企業でも退職金制度を整備すべき理由
中小企業で退職金制度を導入することで従業員の長期勤続を促し、会社へのエンゲージメント向上といった効果が見込めます。今回は整備すべき理由を紹介します。
採用強化につながる
退職金制度が整備されている企業は求職者にとって魅力的です。
給与や仕事内容が同程度であれば、退職金制度の有無が企業選びの決め手になることもあります。特に中小企業では大企業に比べて待遇面で劣る印象を持たれがちですが、退職金制度を用意することで他社との差別化が可能です。
「この会社なら将来も安心できそうだ」と感じてもらえるため、採用力の強化につながります。優秀な人材を惹きつけるためにも、退職金制度の導入は有効な手段といえるでしょう。
従業員のモチベーション・エンゲージメント向上につながる
退職金制度は従業員の長期的なキャリア形成を支援します。将来的にまとまった退職金を受け取れる見込みがあると、従業員は安心してキャリアを積むことができます。
また、「会社が自分たちの将来を考えてくれている」という安心感から、企業への帰属意識やモチベーションが高まる効果も期待できます。従業員の意欲と忠誠心が高まれば、生産性向上や顧客サービスの質向上といった好循環が生まれます。
離職率低下などの結果につながる可能性がある
退職金制度が整っていることは、従業員の長期定着を促す重要な要因となります。将来の退職金を見据えて「この会社で頑張り続けよう」と思う従業員が増えれば、早期離職の抑止につながります。
また、離職率が下がれば、新たな人材採用や育成にかかるコストの削減にもつながり、組織のノウハウ蓄積も進みます。従業員が定着しやすい職場環境を整えることは、中小企業にとって持続的な成長を支える大きなメリットです。
中小企業でも導入できる退職金制度
「退職金制度」といっても種類は様々です。中小企業が利用できる退職金制度には、国の共済から自社内積立まで多彩な選択肢があります。
中退共や企業型確定拠出年金など、中小企業にも適した退職金準備制度が複数存在する。 ここでは、代表的な制度をいくつか紹介します。
中小企業退職金共済(中退共)
国が運営する退職金共済制度。中小企業でも広く利用されています。
小規模企業共済
中小企業の経営者や役員自身の退職・廃業準備金を積み立てる制度です。
確定拠出年金(企業型DC・iDeCo)
従業員が自ら拠出金を運用し、将来の給付額が決まる年金制度(企業型DCや個人型iDeCoなど)です。
特に導入が簡単で安心感が高いのが「中退共」です。国の補助も受けられるため、中小企業にとって手軽かつメリットの大きい制度となっています。
中小企業の多くが導入する中退共とは?
中小企業退職金共済(中退共)とは、厚生労働省管轄の独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業のための退職金共済制度です。
法律に基づき創設され、中小企業単独では十分な退職金を用意しづらいという課題に対し、国の援助と中小企業同士の相互扶助によって成り立っています。
具体的には、企業が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を外部機関(中退共本部)に納付して積み立てます。そして従業員が退職する際には、本人が中退共本部に請求手続きを行い、退職金が直接本人に支払われる仕組みです。
企業は計画的に掛金を積み立てておくだけで、退職時に多額の一時金を用意する必要がありません。また、国の制度がバックアップするため倒産などの万一の際も安全・確実に退職金が確保できる点も魅力です。
中小企業が活用する中退共の制度概要

中退共の加入条件
中退共に加入できるのは、「中小企業基本法」で定める中小企業に該当する企業です。業種ごとに常用従業員数や資本金の基準があり、例えば製造業・建設業では従業員300人以下または資本金3億円以下、サービス業では従業員100人以下または資本金5,000万円以下などとなっています。一般的な中小企業であればほぼ加入可能な範囲と言えるでしょう。
中退共の加入対象者
中退共の被共済者(加入対象者)は、原則としてその企業の常用従業員全員です。一部の従業員だけを選んで加入させるのではなく、基本的に全正社員をカバーします。ただし契約社員やパートタイマーなど一部の短期・短時間雇用者は加入対象外とすることも可能です。
また、経営者や会社役員は加入不可となっています。
加入までの手続き
加入手続きは、
- (1)従業員の同意取得
- (2)掛金月額の決定
- (3)書類の提出
という流れです。必要な申込書類は金融機関や商工会議所で入手・提出でき、特別な手間なく導入できます。
掛け金の範囲
中退共で設定できる掛金月額は5,000円から30,000円の16通り(5千円刻みで選択)です。企業は従業員ごとに掛金月額を選択可能で、掛金は全額事業主負担です(従業員負担は不可)。
掛金は全額損金算入できるため企業の税負担にもなりません。
掛金額は後から増額・減額も可能です。また、掛金の新規加入時や増額時には、国から一部補助が出る助成制度も用意されています。
給付内容
中退共から支給される退職金は、大きく「基本退職金」と「付加退職金」の2種類に分かれます(両方合わせた金額が受取額)。さらに従業員が在職中に亡くなった場合は「死亡退職金(死亡一時金)」が遺族に支給されます。
基本退職金
基本退職金は、企業が積み立てた掛金に基づいて支給される退職金の基本部分です。支給額は「掛金月額 × 掛金納付月数」に応じてあらかじめ定められており、制度全体として年利1%の運用利回りを見込んで設計されています。
例えば掛金月1万円の場合、10年で約120万円、20年で約260万円の基本退職金が支給されます。長期勤続者ほど受取額が掛金総額を上回る利息分が付与され、42ヶ月以上の納付で元本超えとなるよう設計されています。
ただし、勤続1年未満で退職した場合は支給されず、1年以上2年未満では掛金総額を下回る減額支給となります。
付加退職金
付加退職金は、運用利回りが予定を上回った場合に基本退職金に上乗せして支給される退職金です。長期加入者ほど有利に加算されますが、運用状況によっては支給されない年もあり、必ず支給される保証はありません。
なお、会社が独自に基本退職金に上乗せの退職金を支給する(社内規程で加算する)ことも可能です。
死亡一時金
死亡退職金は、退職時に支給されるはずだった金額に一定額を加算して遺族に一時金として支給されます。万一の場合にも遺族への手当が手厚く用意されている点は、中退共制度の安心材料です。
中小企業が中退共を活用した際の退職金額
中退共に一定期間加入した場合、従業員がどの程度の退職金を受け取れるのか、モデルケースを紹介します(掛金月額1万円の場合)。
加入して10年後の退職金
勤続10年(掛金月1万円想定)では約120万円の退職金を受け取ることができます。比較的短期間でも掛金累計額(120万円)を上回る金額が支給され、中退共の利息効果によって老後資金形成に役立ちます。
加入して20年後の退職金
勤続20年では約260万円の退職金となり、掛金累計額(240万円)に対し約11%増の利息分が付加されます。中退共では勤続年数が長いほど上乗せ効果が大きいため、長期勤続するほど退職金額が増加する点が特徴です。
定年退職した際の退職金
定年退職(35年勤務想定)では400万~500万円規模の退職金を受け取ることも可能です(掛金月1万円の場合)。中退共を活用すれば、中小企業の従業員でも数百万円のまとまった退職金を確保でき、長年勤めた労に報いることができます。
中退共を活用するメリット
実際に企業が中退共を活用するメリットを紹介します。
退職金制度の導入ハードルが低い
中小企業が独自に退職金制度を設計・運用するには専門知識が必要であり、煩雑な手続きや多額の資金が必要になる場合があります。
しかし、中退共を利用することで制度設計の手間を大幅に省けるほか、国の機関が後ろ盾となるため安心感があります。
掛金の一部助成が受けられる
企業規模や新規加入状況によっては、国から掛金の一部助成を受けることができます。コストを抑えながら退職金制度を整備できる点は中小企業にとって大きなメリットです。
社会保険料の負担が増えない
退職金の積み立てとして中退共を利用する場合、社会保険料の算定には影響を与えません。給与や賞与を増やすよりも負担を抑えながら、従業員に対する将来保障を充実させることが可能です。
従業員定着率の向上
退職金制度の有無は、従業員が安心して働ける環境を整えるうえで重要な要素のひとつです。制度を導入することで、離職率の低下や優秀な人材確保につながりやすくなります。
中退共のデメリット・注意点
実際に企業が中退共を活用する際のデメリットと注意点を紹介します。
掛金の上限がある
中退共では、掛金月額の上限が決まっています。そのため、高額な退職金を準備したい場合や、キャリアの長い従業員に対する十分な給付を行いたい場合には、制度だけでは不十分になるケースがあります。
途中解約が不利になる場合も
企業や従業員が制度を途中でやめたり、一時的に退職金を引き出したりすると、掛金の積立効率が下がり、思ったように給付額が増えない可能性があります。長期的に利用することが前提の制度である点には注意が必要です。
退職金以外の保障が手薄
中退共は、あくまでも退職金を目的とした制度です。病気やケガ、死亡時の保障、働けなくなった場合の所得補償などについてはカバーできないため、従業員のトータルな保障としては不足感が残ります。
掛金の変更や設計が制限される
中退共では、企業の状況や従業員のニーズに応じて柔軟に掛金を設計・変更することが難しい場合があります。独自性を重視する企業にとってはカスタマイズ性がやや物足りないと感じることがあるでしょう。
中退共だけでは足りない可能性がある理由と保険の活用

前述のデメリットからも分かるように、中退共だけでは従業員の生活保障を十分にカバーしきれないケースがあります。特に以下のような点を補完するために、保険の活用を検討しましょう。
従業員のライフプランに合わせた柔軟な設計
中退共では画一的な掛金設定となるケースが多いですが、保険を活用することで、役職や家族構成、将来設計など従業員一人ひとりに応じたカスタマイズが可能です。
従業員満足度の向上はもちろん、企業としても多様なニーズに対応しやすくなります。
死亡・高度障害保障の備え
従業員に万が一のことがあった場合、中退共では退職金が準備されるだけで、死亡保障としては限定的です。生命保険や収入保障保険などを追加することで、遺された家族の生活費や子どもの教育費をしっかりとカバーすることができます。
働けなくなった場合の生活保障
病気やケガで長期間働けなくなったとき、企業が支払う休業補償や従業員自身の収入減を補う制度がなければ、大きな負担が企業・従業員双方にかかります。就業不能保険や傷害保険などを組み合わせることで、より手厚い保障が実現します。
企業リスクの分散
保険を併用することで、企業がまとめて負担する退職金や弔慰金などの財政リスクを保険会社と分担できるメリットがあります。経営環境の変化に左右されにくく、企業財務の安定にも寄与します。
中小企業の退職金制度まとめ
退職金制度を導入するメリットや、中退共を活用した場合の退職金モデルケースも取り上げました。
人材の採用力強化・定着率改善など、多くのメリットを企業にもたらします。
その実現手段として中退共の活用は、中小企業にとって安全・確実で手軽な選択肢です。国の援助を受けながら計画的に退職金を積み立てられるため、従業員にも会社にも大きな安心をもたらします。
中退共は中小企業が手軽に退職金制度を導入できるメリットがある一方、掛金上限や保障内容の限定などのデメリットも存在します。
そのため、企業としては「中退共だけで完結しているから大丈夫」という考え方ではなく、従業員の多様なライフイベントや万が一のリスクに備えるために、保険を活用したプラスアルファの保障を検討することが重要です。
従業員の安心を高める手厚い福利厚生は、企業への信頼感やロイヤルティ向上に直結し、人材定着率や採用力の強化にも大きく寄与します。
企業の成長と従業員の将来をともに支える仕組みとして、中退共と保険を上手に組み合わせた総合的な福利厚生制度の整備をぜひご検討ください。
当社インプレームのマネーリペアも検討してみてください。
退職金制度の導入で、貴社の人材戦略をさらに強化しましょう!


- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
資料ダウンロード