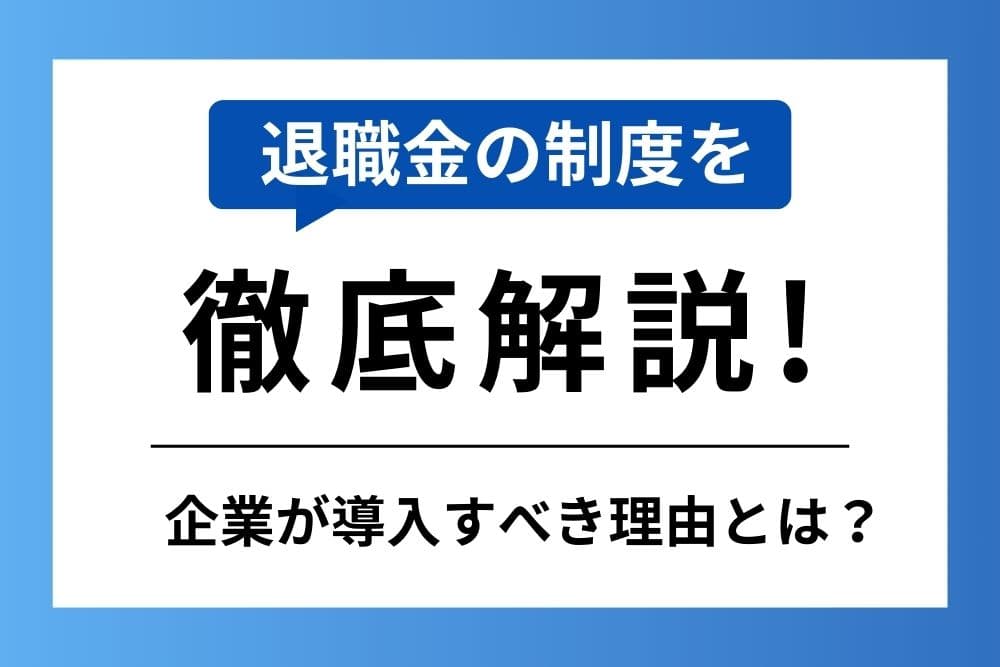お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
退職金なしの企業は従業員からどう考えられるのか?
 詳細を見る
詳細を見る
退職金制度がない企業の割合
従業員側が退職金制度を企業側に求める理由
企業側が退職金制度を整備しない理由
企業側が退職金制度を整備するメリット
多くの社員にとって「退職金」は老後の生活を支える大切な蓄えです。
しかし昨今、あえて退職金制度を設けていない企業も見受けられます。従業員は退職金なしの会社に不安を感じるものなのでしょうか?
本記事では、退職金制度がない企業の現状と背景を明らかにし、企業側・従業員側それぞれのメリットとデメリットを解説します。
制度導入による効果や、制度がなくても行える資産形成支援策にも触れ、双方にとって最適な選択肢を考えてみましょう。
目次
退職金制度がない企業の割合
大企業で退職金制度がない企業の割合
大企業では退職金制度を導入しているケースが圧倒的に多く、退職金制度が「ない」企業はごく少数です。
厚生労働省の調査によると、従業員1,000人以上の大企業で退職金制度を持たない企業は全体の約9%にとどまります。
裏を返せば9割以上の大企業が何らかの退職金制度を整備している状況です。これは日本型の終身雇用・年功序列文化が根強く、従業員の長期勤務を前提とした福利厚生を重視する企業が多いためでしょう。
退職金制度がない大企業の特徴としては、外資系企業やベンチャー企業など、従来の日本的慣行にとらわれずグローバル基準で報酬設計している企業が挙げられます。
こうした企業では、「退職金よりも毎月の給与や賞与で報いる」「株式報酬や確定拠出年金(401kなど)で代替する」などの方針をとり、あえて伝統的な退職金制度を導入しないケースがあります。
とはいえ、大企業全体で見れば退職金制度なしは少数派であり、大半の大企業は従業員に退職金という形で長年の貢献に報いる仕組みを整えているといえます。
中小企業で退職金制度がない企業の割合
一方、中小企業では退職金制度を導入していない企業の割合が比較的高くなっています。厚労省調査によれば、従業員30~99人規模の企業では約30%が退職金制度なしです。
従業員規模100~299人では約15%、300~999人では約11%が退職金制度なしとなっており、規模が小さいほど未整備の割合が増える傾向が明らかです。つまり企業規模が小さいほど「退職金なし」は珍しくないのが現状です。
中小企業で退職金制度がない背景には、コスト面の制約があります。退職金を支給するには長期的な資金準備が必要となるため、体力の限られた小規模企業ではその負担が重くなりがちです。
このため「退職金の代わりに給与や賞与をやや高めに設定する」「福利厚生の充実に振り向ける」など、限られた原資を別の形で従業員に還元しているケースも多いようです。
また、業種による差も見られ、例えば宿泊・飲食サービス業では退職金制度導入率が5割未満と他業種より低い水準にとどまります。
反対に製造業や金融業では8~9割の企業が退職金制度ありと、高い導入率を誇ります。このように、中小企業では業種や企業方針によって退職金制度の有無が分かれますが、全体として約4社に1社は退職金制度なしであることを念頭に置く必要があります。

自社が退職金制度を持っていない中小企業に該当する場合、現在の給与体系や福利厚生が従業員の安心感に繋がっているか再確認してみましょう。退職金がない分をどのように補完するかは、採用や定着にも影響する大切なポイントです。
従業員側が退職金制度を企業側に求める理由
老後に不安がある
退職金制度を社員が望む最大の理由は、老後生活への不安です。公的年金だけでは十分な生活資金を賄えない可能性がある中、退職時にまとまったお金を受け取れる退職金は大きな安心材料となります。
近年「老後資金2000万円問題」という言葉が話題になったように、多くの人が老後に必要なお金の確保に不安を抱えています。現役世代では日々の生活費や住宅ローンなどで精一杯で、なかなか長期の貯蓄ができないという事情もあるでしょう。
そこで会社から退職金が支給されることにより、老後資金の一部が自動的に確保できるため、従業員にとっては将来への安心感が高まるのです。
また、退職金は勤続年数に応じて増えていくため、長く勤め上げれば老後にまとまった報酬を得られる計画が立てられます。もし退職金がなければ、自分で毎月コツコツと老後資金を積み立てる必要がありますが、それには強い意志と計画性が求められます。
「自分では十分に準備できるか不安…」という社員にとって、退職金制度の存在は老後に対する心配を大きく和らげるものとなるでしょう。
将来の見通しが立たないことから企業に頼りたい
社会経済の先行きが不透明な現代、個人で将来の見通しを立てるのは容易ではありません。賃金の伸びや物価、年金制度の将来など不確定要素が多い中、社員としては自分一人の力で長期間の資金計画を立てることに不安を感じるものです。
そのため、「将来のことは会社にも支えてほしい」という心理が働きます。退職金制度があれば、会社が自分の将来に一定の責任を持ってくれると感じられるため、安心感につながります。
特に新卒で入社し長年勤める社員にとって、退職時に報奨として退職金がもらえることは「会社が自分を大切に扱ってくれている」という信頼感にも直結します。
逆に制度がない場合、「この会社で長く働いて将来大丈夫だろうか」という不安から転職を考えてしまうこともあるでしょう。従業員が安心してキャリアを積める環境を示すうえで、退職金制度は重要な役割を果たしているのです。
一人で資産形成や運用ができない
日本の多くの労働者は、投資や資産運用の専門知識を持っていません。自分一人で老後資金を計画的に積み立て、運用で増やしていくのはハードルが高いのが実情です。銀行預金の金利は長らく低水準が続き、ただ貯めるだけではお金は増えません。しかし投資となるとリスクもあり、知識がないままでは躊躇する人が大半でしょう。
こうした中で、会社に退職金制度があれば、社員自身が詳しい運用知識を持たずとも強制的に老後資金の積み立てができるメリットがあります。
退職金制度はある意味「会社主導の資産形成策」とも言え、社員は日々の仕事に専念しながら将来の蓄えを作れるのです。特に金融リテラシーに自信のない社員ほど、「退職金制度がないと自分では老後資金を用意できる気がしない」と感じる傾向があります。こうした理由からも、多くの従業員が会社に退職金制度の整備を求めるのです。
企業側が退職金制度を整備しない理由
余計なコストを削減できる
企業が退職金制度をあえて設けない最大の理由は、コスト削減効果が大きいことです。退職金を支給する前提で人件費設計をすると、その分の資金を将来に備えて積み立てたり準備したりしなければなりません。
例えば自社で内部留保として積み立てておく場合、それは会計上は利益計上されて法人税の対象にもなりますし、外部の企業年金や共済制度を利用する場合も毎年掛金を払い込む必要が生じます。
どちらにしても退職金のために追加の資金負担が発生するわけです。
一方、退職金制度がなければそうした負担は一切不要です。退職金準備のための内部留保や外部掛金をゼロにできるため、浮いた資金を日々の運転資金や成長投資に回すことができます。
また退職金支給がない分、毎年の人件費見通しも立てやすく、余計な将来負担を抱え込まずに済みます。中小企業などでは、このコスト削減のメリットは非常に大きく、利益率の維持や資金繰りの安定に直結します。
「まずは会社を存続・成長させることが最優先」という経営判断から、退職金制度を敢えて持たない選択をするケースも多いのです。
退職時期にあわせた資金繰りが必要ない
退職金制度がある企業では、従業員の退職タイミングに応じて多額の支出を用意する必要があります。特に勤続年数の長い社員が定年などで一斉に退職する際には、一人当たり数百万円~数千万円規模の退職金を同時期に支払う可能性があります。
これに備えて企業は事前に引当金を積み立てたり、退職が重なる年度は資金計画を綿密に立てたりしなければなりません。
退職金制度がなければ、こうした退職時期に左右される資金繰り対応が不要になります。中途退職者が出るたびに退職金を計算して支払う手間や、その支出によるキャッシュフローへの影響を心配する必要もありません。
極端な話、いつどれだけの社員が辞めても、給与の支払い以外に突発的な出費が発生しないため、資金計画が非常にシンプルになります。
特に規模の小さい会社ほど、一度に何人も退職者が出て多額の退職金支払いが重なると経営を圧迫しかねません。そのリスクをそもそも排除できる点で、退職金制度を設けないことは経営の安定策とも言えるでしょう。
運用会社などとのコミュニケーションコストが発生しない
退職金制度、とりわけ企業年金(確定給付年金)や退職金共済などの外部制度を導入すると、その運営・管理のための事務手続きやコミュニケーションコストが発生します。
例えば企業年金を導入すれば、信託銀行や保険会社など運用機関とのやり取り、掛金の算出・送金手続き、制度改定時の協議など、専門的な対応が求められます。
また自社で退職金規程を設けて内部留保する場合でも、毎期の退職給付引当金の計上や、退職金計算の事務など、人事・経理部門の負担が増します。
退職金制度を持たなければ、そうした煩雑な運用管理業務から解放されるメリットがあります。人事担当者は退職金規程や年金制度の管理に時間を割かずに済み、他の業務に注力できます。
特に小規模企業では専門知識を持つスタッフが不足していることも多く、退職金制度を運営すること自体が負担になるケースもあります。
その点、制度なしであれば社外の年金機構や共済機関とのやり取りも不要で、人事・総務の事務作業をシンプルに保てるのです。制度運営にかかる人的コストや時間コストをゼロにできるのは、経営資源の有効活用という観点で見逃せない利点と言えるでしょう。
退職金制度の有無は企業戦略や財務状況に応じた判断が必要です。「制度を持たないことで得られる軽減効果」と「制度を持たないことによるリスク」のバランスを経営陣で定期的に見直し、最適な報酬設計になっているか検討してみましょう。
当社株式会社インプレームでは「マネーリペア」という金融教育に特化した福利厚生サービスを提供しています。1人当たり500円の料金で、専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。
企業側が退職金制度を整備するメリット
税額を調整できる
退職金制度を導入することで、税務面でのメリットを享受できる場合があります。
企業が外部の退職金制度(企業年金や中小企業退職金共済など)に加入し掛金を拠出すると、その掛金は全額が損金(経費)扱いとなり課税所得を減らすことができます。
つまり、同じ人件費を支払うにしても給与として払うより退職金制度に積み立てたほうが法人税の負担を軽減できる可能性があるのです。また退職金として支給するお金には社会保険料がかからないため、企業・従業員双方にとってトータルのコストを抑えられる利点もあります。
加えて、企業によっては退職金制度の導入時に国から助成金を受けられるケースもあります。中小企業が中小企業退職金共済に新規加入するときなど、一定の条件下で国が掛金の一部を補助してくれる制度が存在します。
さらに退職金を支給すればその分利益が圧縮され、利益調整の手段として活用できる側面もあります(もちろん恣意的な操作はできませんが、計画的な引退金支出で税負担の平準化を図ることは可能です)。
このように、退職金制度は従業員のためだけでなく企業の税務戦略上も有利に働く部分があるため、節税対策の一環として導入を検討する経営者もいます。
採用力強化につながる
求職者にとって退職金制度がある会社は魅力的に映ります。求人情報でも「退職金制度あり」は福利厚生の充実度を示すポイントの一つです。
特に経験豊富な中途採用者や、将来長く腰を据えて働きたいと考える人にとって、退職金制度の有無は企業選びの重要な判断材料になりえます。実際、同程度の給与水準なら「将来の安心」を提供してくれる会社を選びたいと考える人は少なくありません。
そのため、退職金制度を整備することは人材獲得競争におけるアピールポイントになります。「社員の将来を考え、当社は退職金制度を用意しています」と胸を張って言えることは、企業の魅力アップにつながります。
優秀な人材ほど、自身のキャリアプランを長期的に考えて企業を選ぶ傾向があるため、退職金制度があるかどうかで応募者数や内定承諾率に差が出ることもあります。
また、新卒学生の保護者世代から見ても退職金制度が整っている会社は安心感があるため、家族の後押しを得やすいといった効果も期待できます。総合的に見て、退職金制度の導入は企業の採用ブランド力を高め、人材確保を有利に進める追い風となるでしょう。
離職率などの指標が下がる可能性がある
退職金制度は社員の定着率向上にも寄与します。勤続年数に応じて退職金額が増える仕組みであれば、「もう少し頑張って勤め続けよう」という動機づけになり、安易な離職を防ぐ効果があります。特に中堅以降の社員にとって、退職金は在職中には得られない将来の大きな報酬です。
そのため、退職金制度がしっかりある会社では社員が長期的視野で働く傾向が強まり、結果として平均勤続年数が延びたり離職率が低下したりするケースが見られます。
また、退職金制度は社員のロイヤリティ(忠誠心)を高める側面もあります。「この会社に貢献すれば自分にも最後にしっかり報いてくれる」という安心感が、日々の仕事へのコミットメントにつながるのです。
モチベーション維持の観点でも、退職金という将来のインセンティブがあることで目の前の業務にも前向きに取り組めるという社員は少なくありません。社員満足度の向上とそれによる生産性アップという好循環も期待できるでしょう。
もちろん退職金制度が万能薬ではありませんが、制度がない企業と比べれば「長く勤めたい」「ここでキャリアを築きたい」と社員に思ってもらいやすくなるのは事実です。
結果として有能な人材の流出を防ぎ、組織力の安定強化につながる可能性があります。退職金制度の整備は、目に見える数字(離職率や勤続年数)の改善という形で効果が現れることも多いのです。

退職金制度の導入はコスト負担も伴いますが、それ以上に得られる効果(採用・定着・社員の安心感向上など)を考慮して検討する価値があります。自社の将来ビジョンに照らし、退職金制度が企業成長に寄与するかを戦略的に評価してみましょう。
企業側が退職金制度を整備しないままにするデメリット
従業員の勤労意欲が下がってしまう
退職金制度がない企業では、従業員の勤続意欲やモチベーションの低下が懸念されます。退職金は長年の勤務に対する報奨であり、「将来これだけもらえるから頑張ろう」という一種の目標になります。
制度がない場合、社員にとって勤続年数によるメリットが感じられず、「このままここに居続ける理由が薄い」と思われてしまう可能性があります。
特に同業他社が退職金制度を持っている場合、待遇面で見劣りする会社からは人が流出しやすくなります。「どうせなら退職金のある会社に転職したい」と考える社員が出てきても不思議ではありません。
また社内においても、「自分は将来会社から何ももらえないのか」という不満や不信感が蓄積すると、日々の仕事への意欲に影響します。
給与や賞与が出ていても、長期的な恩恵がゼロであることが分かっていると、途中で力尽きてしまう社員が増える恐れがあります。これは企業にとって生産性の低下や優秀な人材の離脱に直結する大きなデメリットです。
つまり、退職金制度なしは短期的には問題なくても、長期的に見れば社員のエンゲージメント(会社への愛着)を下げてしまうリスクをはらんでいます。従業員のやる気低下は業績にも跳ね返ってくるため、制度未整備による影響を軽視すべきではありません。
節税に関するメリットを得られない
前述のように、退職金制度には税制上の優遇がある場合があります。しかし制度を整備していないと、そうした節税メリットを一切享受できません。
例えば企業年金や退職金共済に掛金を払っていればその分課税所得を減らせたものが、制度未加入だと全額が利益として残り法人税の課税対象になります。
また、退職金を支給すれば社会保険料負担が発生しない部分も、制度がなければ同額を給与で支給するしかなく社会保険料の負担増につながります。
さらに、退職金制度がある企業のみ対象となる各種助成金(中小企業退職金共済の新規加入助成など)も、制度がなければ当然受けられません。
節税や助成を通じて資金効率を上げるチャンスを逃しているとも言えます。中長期的に見れば、退職金制度なしで払い続けた税金や保険料の総額が相当大きくなっているケースも考えられるでしょう。
経営上、「余計なコストをかけたくない」という理由で制度未整備にしている場合でも、トータルでは損をしてしまっている可能性がある点には注意が必要です。
単年度では見えにくい部分ですが、長期スパンで試算すると、制度導入による税負担軽減効果が企業財務にプラスだったということも起こりえます。制度を持たないことで失っているメリットがないか、検証してみることも大切です。
採用のPRポイントが減る
退職金制度がないと、人材採用時のアピール材料が一つ減ってしまいます。求人票や会社説明の場で、「当社には退職金制度があります」と伝えられることは、それだけで求職者に安心感や魅力を与えます。
逆に制度がない企業は「当社は退職金制度はありませんが…」と補足説明が必要になる場合もあり、どうしても印象として不利になりがちです。
特に同業界で競合他社が福利厚生を充実させている場合、退職金制度の有無は明確な差となります。求職者からすると、給与や仕事内容が似通っていれば少しでも条件の良い会社を選びたいと思うのが自然です。
その際に退職金制度なしはマイナス要因となり、せっかく良い人材が応募してくれても「福利厚生面で不安」と辞退されてしまうケースも考えられます。
また、新卒採用でも親世代や学校の就職指導担当者から「退職金制度がない会社は大丈夫か」と心配されることもあります。企業イメージとしても、「従業員思いではないのでは?」と疑念を抱かれかねません。
退職金制度がないことで採用PRの武器が減り、競合他社に遅れをとる可能性がある点は、企業にとって見過ごせないデメリットでしょう。
退職金制度がない企業で働く従業員側のメリット
退職金に関わる手続きをしなくて済む
退職金制度がない職場で働くことには、社員側にもいくつかメリットが存在します。まず挙げられるのが、退職金の受け取り手続きが不要な点です。
通常、退職金を受け取る際には会社から「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出してもらい、適切な税金計算を行う必要があります。
もしこの手続きを怠ると、自分で確定申告して税金の清算をしなければならず、退職直後に煩雑な作業が発生します。
退職金制度がない企業であれば、そもそもそのような書類手続きが発生しません。退職時は最終給与の受け取りや社会保険の手続き程度で済み、身軽に次のステップへ進めるメリットがあります。
特に転職や独立など、退職後の計画がすでにある人にとっては、退職金の支給待ちや税務処理に時間を取られないのは利点と言えるでしょう。
また、会社側の都合で退職金支給が遅れたり計算ミスが起きたりといったトラブルとも無縁です。身一つでスムーズに退職できる気軽さは、退職金制度がない環境ならではのメリットと言えます。
給与や賞与水準が高い可能性がある
退職金制度を設けていない企業の中には、退職金を出さない代わりに月々の給与やボーナスに上乗せして支給しているところもあります。
退職金原資分を平時の報酬に組み込んでいるため、同業他社と比べて基本給や賞与額が高めに設定されているケースです。社員からすれば毎月の収入が多い方が生活にゆとりが生まれますし、自分で運用する余力も増えます。
特に若いうちから資産形成を始めたい人や、マイホーム購入・子育てなどで早期にお金が必要な人にとって、退職時まで待たずに報酬を受け取れるメリットは大きいでしょう。
退職金は通常何十年も勤続しなければ満額もらえませんが、制度なしでその分を毎年受け取っていれば、自ら運用して増やすチャンスも得られます。仮に投資が得意な人であれば、会社に預けっぱなしにするより自分で資産運用した方が効率的と考える場合もあるでしょう。
また、退職金制度ありの場合は途中退職すると勤続年数に応じた割合しかもらえませんが、制度自体がなければ転職しても「もらい損ね」がないとも言えます。
その分、在職中にしっかり給与として受け取っているからです。
総じて、退職金制度がない企業で働くことは
- 「毎月の手取りを最大化できる」
- 「将来の報酬を自分の裁量で運用できる」
というメリットにつながる場合があります。
もちろん企業によって給与水準は様々ですが、制度なしの分だけ待遇面で別の恩恵がある可能性を考慮すると、必ずしも社員にとって一方的なデメリットとは言えないでしょう。
退職金制度がない企業であっても福利厚生で資産形成をサポートできる
企業に退職金制度がなくても、他の福利厚生制度を活用して従業員の資産形成を支援する方法があります。代表的なものが確定拠出年金(企業型DC)です。
これは会社が従業員ごとの年金口座を用意し、毎月一定額を拠出する制度で、社員自身が運用先を選んで老後資金を準備します。企業型DCを導入すれば、従業員は退職金の代わりに在職中から自分名義の年金資産を積み立てることができます。
掛金は全額非課税で拠出され、運用益も非課税(一定条件下)という税制優遇があるため、社員にとって効率的な資産形成手段となります。企業にとっても掛金は損金計上でき、退職金のように一度に多額を支給する必要がないなどメリットがあります。
また、社員持株会の制度も有効な代替策です。社員が毎月給与天引きで自社株を購入する仕組みで、会社が奨励金を上乗せしてあげるケースもあります。
持株会を通じて社員は自社の成長を自分の資産形成に直結させることができます。株価が上がれば資産も増え、配当金も収入になります。退職時には貯まった株式を売却することで、ある種の「退職金」のような役割を果たすことも可能です。
そのほか、財形貯蓄制度(勤労者財産形成貯蓄)を設ける企業もあります。給与から天引きで積み立てを行い、一般財形・住宅財形・年金財形と目的に応じて貯蓄できる制度で、年金財形なら5年以上積み立てて60歳以降に受け取る場合利子等が非課税になります。
会社が財形貯蓄利用者に奨励金を出したり利子補填をしたりするケースもあり、退職金代わりに財形で老後資金準備を促すことも一つの方法です。
中小企業であれば、中小企業退職金共済(中退共)への加入も検討できます。これは国の機関である勤労者退職金共済機構が運営する共済制度で、企業が毎月拠出した掛金が従業員ごとの退職金として積み立てられます。
社員が退職する際には機構から直接共済金(退職金)が支払われるため、企業は負担した掛金以上の支払い責任を負いません。国からの掛金助成もあることから、独自に退職金制度を持てない中小企業でも外部制度を利用して退職金相当額を用意できる仕組みです。
このように、退職金制度がなくても
- 企業型DC
- 社員持株会
- 財形貯蓄
- 退職金共済
など代替となる福利厚生制度を組み合わせることで、従業員の将来の資産形成をサポートすることは十分可能です。
重要なのは、「退職金がない代わりに当社はこうした制度で皆さんの老後準備を支援します」と社員に示し、安心して働ける環境を整えることです。会社の規模や財政状況に応じて、最適な施策を選択していきましょう。
退職金まとめ
退職金制度がない企業の現状と課題について、企業側・従業員側双方の視点から考察してきました。
大企業では退職金制度があるのが当たり前という風潮の中、一部ではコスト削減やグローバルスタンダードを理由に制度を持たない企業も存在します。
中小企業では約4社に1社が退職金制度なしという実態があり、特に規模が小さいほどその傾向が顕著です。
従業員にとって退職金制度は老後の安心を支える大きな柱であり、制度がないことに不安を覚える声は根強くあります。
社員に「会社が自分たちの将来に配慮してくれている」と感じてもらえる仕組みを提供することです。退職金制度の有無を含めた福利厚生の整備は、企業文化や人材戦略にも関わる重要なテーマです。
専門家の意見を取り入れつつ、自社のビジョンに沿った制度設計を進めていきましょう。
当社株式会社インプレームでは「マネーリペア」という金融教育に特化した福利厚生サービスを提供しています。1人当たり500円の料金で、専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
資料ダウンロード