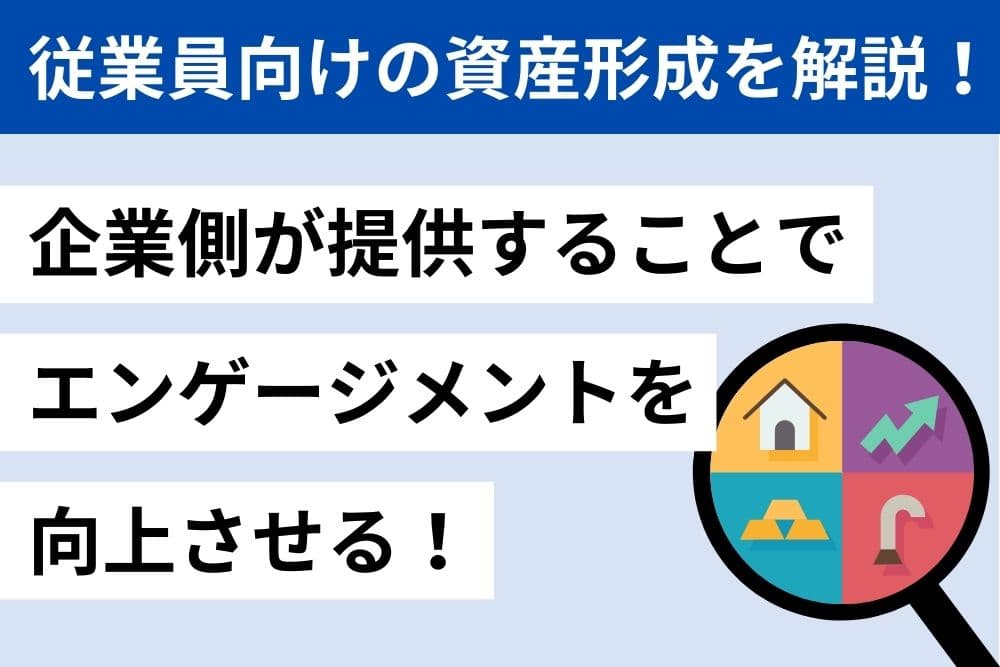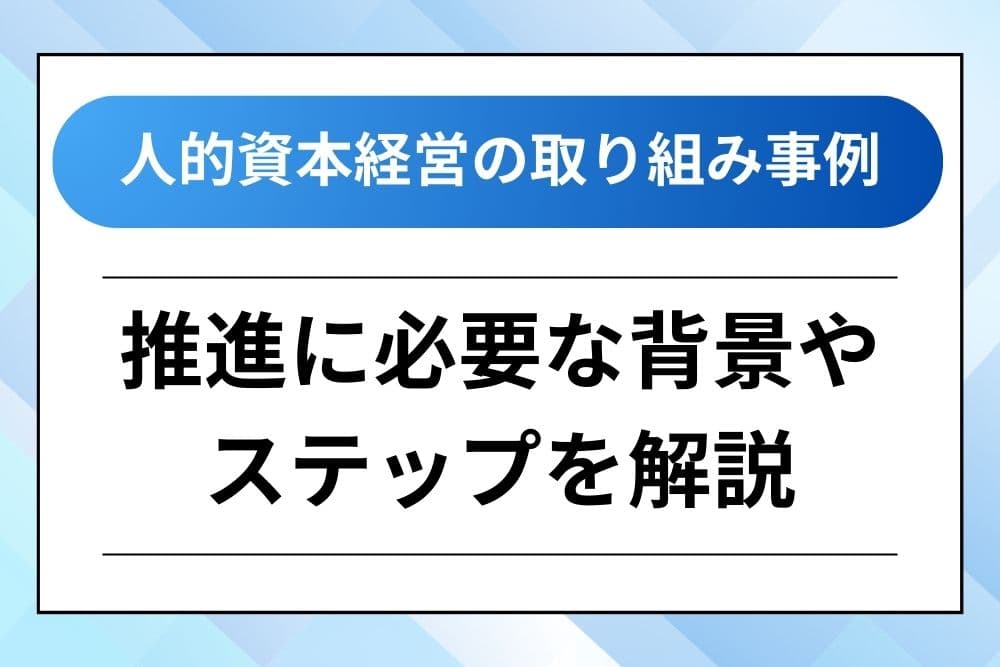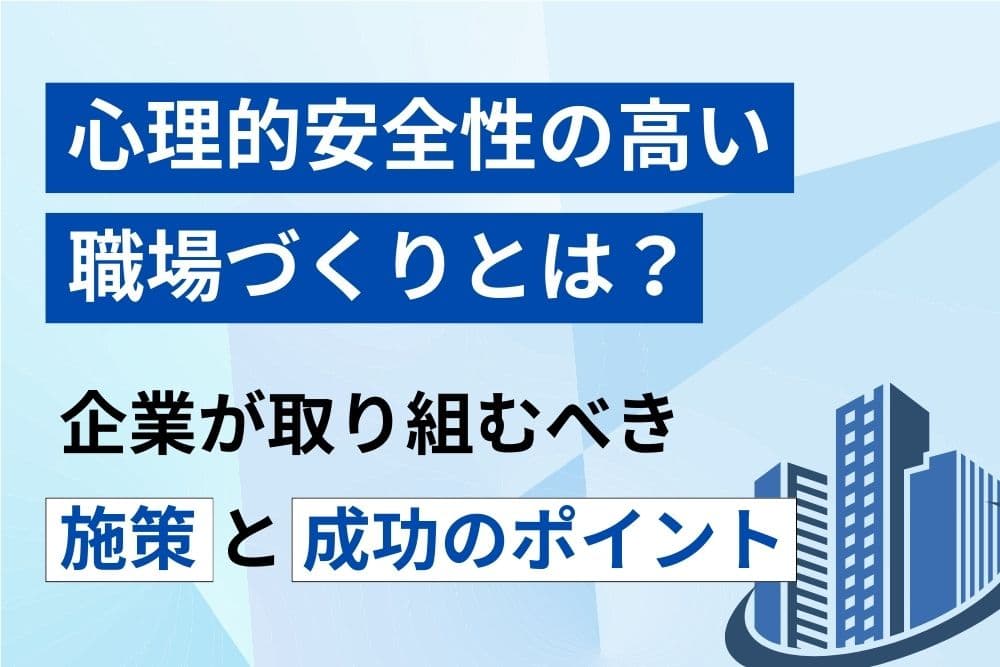お役立ち情報
- 株式会社インプレーム
- # 福利厚生
福利厚生での資産形成とは?投資型福利厚生で人材戦略に活用できる!
 詳細を見る
詳細を見る.jpg&w=1080&q=75)
福利厚生での資産形成の種類
福利厚生として資産形成を提供するメリット
福利厚生として企業側が資産形成を提供するデメリット
福利厚生として資産形成を提供している企業の割合
財形貯蓄制度などを導入する手順と方法
企業の競争力を高めるには、従業員の満足度向上と長期的な定着が欠かせません。その手段として今注目されているのが「投資型福利厚生」です。
従来の福利厚生は、健康保険やレジャー施設の割引といった消費型が中心でしたが、最近では従業員の資産形成を支援する制度が導入され始めています。
資産形成とは、将来に備えて計画的に貯蓄や投資を行い、個人の資産を増やしていくことです。
財形貯蓄、企業型確定拠出年金、持株会などの制度を活用すれば、従業員は給与の一部を積み立てながら効率的に資産を増やせます。
企業側も、税制優遇を受けながら従業員の経済的安定を支援でき、結果的に人材流出の防止や採用競争力の向上につながります。
本記事では、資産形成を目的とした福利厚生の仕組みと活用法について詳しく解説します。
目次
福利厚生での資産形成の種類

福利厚生での資産形成とは、従業員の資産作りを会社が福利厚生制度としてサポートすることを指します。
具体的には、
- 給与天引きによる貯蓄制度
- 社員向けの年金制度
- 持株会の設置
- 社内でファイナンシャルプランナー(FP)による金融教育や個別相談の機会を提供
することなどが含まれます。
従業員にとって、会社経由で資産形成を行うメリットは大きいです。
給与から自動的に貯蓄ができればムリなくお金を貯められますし、税制優遇のある制度を活用すれば効率よく資産を増やすことができます。また、将来の住宅購入資金や老後資金を計画的に準備できるため、生活設計(ライフプラン)を立てやすくなるでしょう。
企業側にとっても、従業員の経済的な安心は仕事への集中力向上や定着率アップにつながります。以下では、福利厚生として提供される代表的な資産形成支援策について、その仕組みやメリット・デメリットを解説します。
福利厚生による資産形成制度の比較
運用方法
税制優遇
流動性
企業の負担
従業員の負担
一般財形貯蓄
給与天引きで貯蓄(元本保証)
なし(利息に課税)
3年以上積立で自由に引き出し可能
金融機関との契約・給与天引き管理
給与天引きで貯蓄(可処分所得減少)
財形住宅貯蓄
給与天引きで貯蓄(住宅資金専用)
利息非課税(550万円まで)
住宅取得以外の引き出し不可(5年以上積立)
契約管理・住宅取得時の確認
住宅資金専用(途中用途変更不可)
財形年金貯蓄
給与天引きで貯蓄(60歳以降受取)
利息非課税(550万円まで)
60歳まで引き出し不可
契約管理・退職者対応
老後資金専用(途中引き出し不可)
企業型確定拠出年金
企業拠出+従業員運用(投資信託等)
掛金非課税・運用益非課税・受取時控除あり
60歳まで引き出し不可(転職時は移管)
掛金負担・運営管理費・投資教育
自己運用リスクあり・60歳まで引き出し不可
持株会
給与天引きで自社株購入(奨励金あり)
奨励金あり(税優遇なし)
売却可能(企業のルールにより制限あり)
奨励金負担・持株会運営コスト
株価変動リスク・資産集中
一般財形貯蓄
一般財形貯蓄は、勤労者財産形成貯蓄制度(通称「財形貯蓄」)の一つで、使途を定めず自由に貯蓄できるタイプの制度です。
従業員が希望する金額を毎月の給与から天引きし、提携する金融機関の財形貯蓄口座に積み立てます。積み立てた資金は住宅購入や老後資金といった特定目的に縛られないため、さまざまな資金ニーズに柔軟に対応できるのが特徴です。
メリットとして、給与天引きにより強制的かつ計画的に貯蓄できるため、「いつの間にかお金が貯まっている」状態を作りやすい点が挙げられます。手元に入る前に貯蓄する仕組みのため、使い過ぎの防止にもなります。
また、運用の知識がなくても銀行預金などで確実に貯められるため、投資に不慣れな若手社員でも安心して利用できます。
企業にとっても、比較的導入コストが低く(給与計算システムに項目を追加する程度)、従業員の福利厚生充実を図れる利点があります。
一方、デメリットもいくつかあります。
一般財形貯蓄には利子に対する税制優遇がなく、預貯金の利息には通常通り課税されます(※財形住宅貯蓄・年金貯蓄には非課税枠がありますが、一般財形にはありません)。
そのため超低金利下では資産が大きく増えるわけではなく、あくまで「貯める習慣づくり」が主目的になります。また、従業員側から見ると途中解約はできるものの、せっかく積み立てたお金を安易に引き出してしまえば資産形成の効果が薄れてしまいます。
企業側としても口座開設や給与天引きの事務手続きが多少発生しますが、後述する住宅・年金財形に比べれば運用ルールがシンプルな分、管理の負担は小さいでしょう。
財形住宅貯蓄
財形住宅貯蓄は、マイホーム取得の資金づくりを目的とした財形貯蓄制度です。基本的な仕組みは一般財形と同様に給与天引きで積み立てますが、資金の使いみちは自宅の新築・購入、増改築といった住宅関連に限定されます。
住宅取得以外の目的で積み立て残高を引き出す場合や、契約から5年未満で解約する場合にはこの制度の恩恵を十分に受けられない点に注意が必要です。
財形住宅貯蓄の大きなメリットは、利息に対する非課税措置です。財形年金貯蓄と合算して元本550万円までの預け入れ残高に対して発生する利息が非課税となり、通常約20%かかる利子所得税がかかりません。
これは長期にわたり計画的に貯蓄を続けるほど恩恵が大きくなる仕組みで、マイホーム資金を効率よく貯めることができます。
また、この制度を利用して一定額(一般的に残高50万円以上)を積み立てていると、独立行政法人住宅金融支援機構等が提供する財形持ち家融資制度を利用できます。
積立残高の最大10倍(上限4,000万円)までの住宅ローンを低金利で受けられる制度で、自己資金が不足していてもマイホーム取得に踏み切りやすくなるでしょう。
デメリットとしては、資金の使途が住宅に限定されるため、途中で目的が変わった場合に使いづらくなる点があります。例えば、当初は住宅購入を考えていたものの転勤や家族の事情で持ち家が不要になった場合、積み立てたお金を他の目的に転用すると非課税のメリットが受けられなくなります。
また、住宅購入まで資金を引き出さずに置いておく必要があるため、急な出費が生じた際に流用できない制約もあります。ただし、マイホーム取得という大きなライフイベントに向けて計画的に資金を準備できる点で、若手社員から中堅社員まで幅広い層に有益な制度と言えます。企業側としては、従業員の住宅取得支援を通じて長期的な定着を促す効果が期待できます。
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄は、老後資金の形成を目的とした財形貯蓄制度です。こちらも給与天引きで積み立てる点は同じですが、基本的に60歳以降まで引き出さずに長期運用し、退職後に年金または一時金として受け取ることを想定しています。
積立期間中は利息が非課税となる点も住宅財形と共通しており、両者あわせて元本550万円までの利息が非課税になる優遇措置があります(例えば住宅財形で300万円・年金財形で250万円積み立てている場合、その合計550万円分までの利息が非課税)。
財形年金貯蓄のメリットは、何と言っても計画的に老後資金を準備できることです。公的年金だけでは不安な将来に備えて、現役時代からコツコツと資金を確保でき、利息非課税の効果で効率よく資産が増やせます。
途中で引き出しができない(60歳まで原則据え置き)ため、「将来の自分への貯金」として確実に残せる点も特徴です。また、運用商品として財形年金保険(生命保険会社の年金保険商品)を選べば、60歳以降に年金形式で受け取ることも可能で、退職後の生活資金計画が立てやすくなります。
一方、デメリットとしては資金の流動性が極めて低い点が挙げられます。原則として60歳になるまで積立金を引き出せないため、急な資金需要に対応できません(※要件を満たさず解約した場合、それまで非課税だった利息に遡って課税されるペナルティがあります)。
若年層の社員にとっては老後は遠い将来のため、この制度の必要性を実感しづらく、加入者が伸び悩む傾向もあります。また、低金利環境では利息自体がそれほど大きくならないため、非課税メリットを享受できる額にも限りがあります。
それでも、人生100年時代と言われる中、老後資金を計画的に準備できる財形年金貯蓄の意義は大きいでしょう。企業としても、従業員が安心して定年まで働ける環境を整える一環として導入を検討する価値があります。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が従業員のために用意する私的年金制度の一つです。従業員それぞれに専用の年金口座を開設し、企業が毎月拠出金(掛金)を拠出します(企業によっては従業員が給与の一部をマッチング拠出できる場合もあります)。
拠出された資金は従業員自身が運用商品(投資信託や定期預金など)を選んで運用し、原則60歳以降にその運用結果に応じた給付(年金または一時金)を受け取ります。いわゆる「日本版401k」とも言われる制度で、2001年に制度化されて以来、多くの大企業で導入が進んでいます。
企業型DCのメリットは、従業員と企業の双方にあります。従業員にとって、掛金は所得税・住民税が非課税となるうえ、運用益も受取時まで非課税で再投資されます(受取時に退職所得控除等の対象)。
つまり、税負担を軽減しながら効率的に老後資金を準備できるのです。また、企業拠出による上乗せの年金が得られるため、公的年金や個人の貯蓄だけの場合と比べて豊かな老後を実現しやすくなります。
運用商品の選択肢も複数用意されており、自分のリスク許容度に応じて元本保証型から株式型まで選べるので、投資経験の浅い社員でも適切な商品を選べます(運用を自分で選ぶのが難しい場合に備えてデフォルト商品が設定されている企業もあります)。
企業側にとっては、確定拠出年金は将来の年金給付額が運用結果に応じて決まるため、コストが確定している点が魅力です。従来の確定給付年金(企業年金)や退職一時金のように、将来の業績悪化時に大きな給付負担が発生するリスクがありません。
毎年の掛金負担額があらかじめ決まっているため、長期的な人件費計画が立てやすくなります。また、掛金は給与とは別枠の福利厚生費扱いのため、企業にとって損金算入できるのはもちろん、一定範囲で社会保険料の対象外となるメリットもあります。
制度を導入することで「社員の老後も面倒を見る会社」というイメージアップにつながり、優秀な人材の確保・定着にも寄与します。
ただし、確定拠出年金には留意点もあります。運用結果次第では将来受け取れる年金額が目減りする可能性があるため、従業員自身が資産運用リスクを負うことになります。
特に運用知識が乏しい社員の場合、適切な商品選択や定期的な運用見直しが行われないと十分な成果を得られない恐れもあります(企業には加入者への教育義務があり、情報提供や研修を実施することが望まれます)。
また、企業にとっても制度運営の事務手続きや金融機関との契約管理などの負担が発生します。しかし、信頼できる運営管理機関やコンサルタントのサポートを得れば、比較的スムーズに導入・運営することが可能です。
持株会
持株会は、従業員が自社の株式を計画的に取得するための制度です。毎月の給与や賞与から一定額を天引きして積み立て、その資金で会社の株式を定期的に購入します。
実際の運用は「○○会社従業員持株会」という組織を通じて行われ、多くの場合、信託銀行や証券会社が事務局となって株式の取り扱いを代行します。
企業によっては、従業員の拠出額に対して一定割合(例:5~10%)の奨励金を上乗せ支給するケースもあり、従業員にとって有利な条件で自社株投資ができるよう工夫されています。持ち株会のメリットは、従業員が自社の成長の果実を直接共有できる点です。会社の業績が向上し株価が上がれば、従業員の資産も増加しますし、配当金を受け取ることで在職中から投資収益を得ることもできます。
自社への帰属意識が高まり、「自分たちの会社を自分たちで盛り上げていこう」というモチベーションにつながる効果も期待できます。
また、給与天引きで少額からコツコツ投資できるため、投資初心者でも取り組みやすい点も利点です。奨励金が支給される場合には、その分だけ確実にリターンが上乗せされるため、従業員にとって非常に有利な福利厚生と言えるでしょう。
一方で、持ち株会にはリスクも存在します。最大のリスクは、従業員の資産が自社の業績に過度に連動してしまう点です。仮に業績不振や株価下落が起きた場合、従業員は給与や賞与の減少といった本業での不利益に加え、自社株の評価額下落というダブルパンチを受ける可能性があります。
資産形成の観点からは、本来は投資先の分散が重要ですが、持ち株会ではどうしても自社株への集中投資になりがちです。そのため、企業側は従業員に対し「持株会への拠出は無理のない範囲で行う」「自社株以外の資産形成手段も併用する」といった教育や情報提供を行うことが望ましいでしょう。
制度面では、従業員が退職した際に持株会から株式を引き出して売却できる仕組みや、業績悪化時に社員の損失を緩和する配慮などが求められます。これらリスクを踏まえつつも、持ち株会は社員と会社の一体感を醸成し、双方にメリットをもたらし得る制度です。
社内ファイナンシャルプランナーを活用した従業員向け投資アドバイス
基本的な仕組み
最近注目されているのが、社内ファイナンシャルプランナー(FP)による従業員向けの投資・マネー相談サービスです。
これは、企業が自社の福利厚生としてFP資格を持つ専門家を活用し、従業員に対して金融に関する教育や個別アドバイスを提供する仕組みです。
具体的には、社内にFPの資格を持った人材を配置したり、外部の独立系FP会社と契約して定期的に相談会を開いたりします。従業員は仕事の合間や就業後に無料もしくは低負担で相談を受けることができ、自分の資産運用やライフプランについてプロのアドバイスを得られます。
また、マネーセミナー(勉強会)を開催して投資や税制の基礎知識を学ぶ機会を提供する企業も増えています。社内FP制度を整えることで、従業員は身近な場所で気軽に専門的な相談ができる環境が整います。
従業員の資産形成に与える影響
FPによるアドバイスは、従業員の資産形成に大きなプラス効果をもたらします。専門家から中立的な立場で助言を受けることで、従業員は自分に合った資産運用方法や保険の見直し、住宅ローンの組み方などを知ることができます。
例えば、FPに「毎月いくらずつ投資信託を積み立てれば将来いくらになるか」「NISAやiDeCoなど税優遇のある制度をどう活用すべきか」といった具体的なプランを立ててもらえるため、漠然とした不安が解消され行動に移しやすくなります。
その結果、これまで預金に眠っていたお金を有効に運用し始めたり、無駄な保険料の支出を見直して貯蓄に回したりと、従業員の資産形成ペースが加速することが期待できます。また、会社から提供されたFP相談を通じて従業員がお金に関する知識を身につければ、将来への漠然とした不安が軽減し、精神的な安心感を得られます。
経済的なストレスが減ることで仕事にもより集中でき、生産性向上にもつながる可能性があります。
企業側が得られる税制優遇のメリット
企業が従業員向けにFP相談や金融教育の機会を提供することは、税務上も有利に扱われる場合があります。従業員個人がFPに相談すると本来は有料で数万円の費用がかかるケースもありますが、福利厚生として会社が一括契約して提供すれば従業員は無料で利用できます。
福利厚生として専門家のアドバイスを提供することは企業にとって費用対効果の高い従業員支援策と言えるでしょう。また、FPのアドバイスによって従業員が適切に資産運用できれば、将来にわたって経済的に自立した社員が増え、結果的に定年後再雇用の負担軽減や退職金準備の計画立案にも好影響を及ぼす可能性があります。
当社株式会社インプレームでは「マネーリペア」という金融教育に特化した福利厚生サービスを提供しています。専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。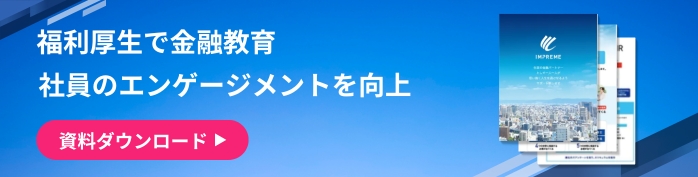
福利厚生として企業側が資産形成を提供するメリット
従業員の金融リテラシーを上げ、業務に良い影響を与える
従業員が資産形成の仕組みを利用する中で、自然とお金に関する知識(金融リテラシー)が向上していきます。例えば、確定拠出年金で運用を始めれば利回りやリスクについて学ぶ機会が増えますし、財形貯蓄を通じて税金や利息の仕組みに関心を持つようになります。
金融リテラシーが高まった従業員は、企業の経営数字や経済ニュースに対して理解が深まり、自部署の業務改善やコスト管理にも良い影響を与えることがあります。
「数字に強い社員」が増えることは、企業にとってプラスです。また、社員が自分の将来の資産計画を立てられるようになると、日々の仕事にも目的意識が生まれ、モチベーション向上につながるでしょう。
さらに、会社が従業員の金融知識向上を支援する姿勢を示すことで、「社員を大切にする会社」というポジティブなイメージを社内外に醸成できます。
社内研修として投資やマネープランの勉強会を開催すれば、従業員同士でお金の知恵を共有し合う文化が生まれるかもしれません。マネーリテラシーの向上は社員個人の資産形成だけでなく、企業全体の生産性や健全な経営感覚の醸成にもつながる重要な要素です。
関連記事:「企業向け金融教育とは?導入メリットや成功事例、実践方法を徹底解説」
人材流出を防ぎ採用コストを抑制する
充実した資産形成支援の福利厚生は、従業員の定着率向上に寄与します。社員にとって、自社で働き続けることで将来の資産形成に有利な制度を享受できるとなれば、安易に転職しようという考えを抑制する効果が期待できます。
特に確定拠出年金の企業拠出分や持株会の奨励金といった仕組みは、在籍している間に積み上がる利益が大きいため、「辞めるともったいない」という心理が働きやすくなります。また、金融相談などきめ細かな支援を受けている社員ほど、自社への愛着が強まり「この会社で長く働きたい」という気持ちが育まれます。
一方で、採用活動の面でもアピールポイントとなります。優秀な人材ほど福利厚生の内容に注目しており、単に給与額だけでなく長期的な成長や安心をサポートしてくれる企業を選ぶ傾向があります。
「財形貯蓄制度や企業型年金あり」「FPによるマネー相談あり」といった情報は求人票や会社説明会で他社との差別化材料になるでしょう。結果として、応募者を集めやすくなり、採用にかかるコスト(求人広告費やエージェント手数料等)の削減にもつながります。
資産形成支援の福利厚生は、人材流出の防止と優秀な人材の獲得という両面から企業の人件費効率を高める効果があります。
関連記事:「福利厚生で資産形成!企業が導入すべき投資型福利厚生の仕組みと成功事例」
従業員のライフプランの見通しを立て、帰属意識・エンゲージメントを向上させる
福利厚生として資産形成支援策を提供することは、従業員一人ひとりが自分のライフプランを明確に描く手助けになります。住宅取得や子供の教育資金、老後の生活費など人生の大きなイベントに対し、会社の制度を活用して準備ができていれば、将来への見通しが立ちやすくなります。
「このまま働き続ければマイホームの頭金が確保できそうだ」「定年までに十分な老後資金を蓄えられそうだ」と実感できることは、従業員に大きな安心感を与えます。
将来への安心感は、そのまま企業への帰属意識につながります。自分の人生設計に会社の制度が深く関与している状態では、従業員は会社に対して感謝や信頼の気持ちを抱きやすくなります。
例えば、財形貯蓄でマイホームを手に入れた社員は、「この制度を用意してくれた会社のおかげだ」という思いから、より一層会社に貢献しようと感じるかもしれません。企業に対するエンゲージメント(愛着心や主体的な貢献意欲)が高まれば、従業員は仕事で主体性を発揮し、困難な局面でも会社と共に乗り越えようとするでしょう。
ひいては顧客に対するサービス向上やイノベーション創出にもつながり、企業価値の向上に寄与するはずです。
資産形成支援の福利厚生で社員のエンゲージメントを高めたい企業様は、ぜひ専門サービスのマネーリペアをご活用ください。
福利厚生で資産形成ならマネーリペア
「自社でこれらを一から用意するのは大変そうだ」と感じた経営者・人事担当の方もいるかもしれません。
マネーリペアは、当社が提供する金融教育に特化した福利厚生サービスで、専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を支援します。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
- プロのFPによる個別相談
- 資産管理ツールの提供
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果もございます。
社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながります。マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。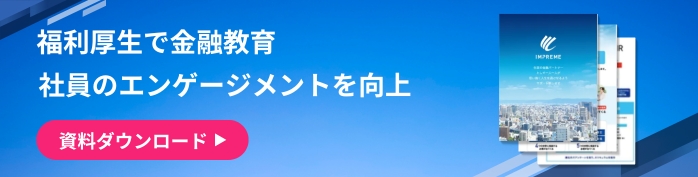
福利厚生として企業側が資産形成を提供するデメリット
事務負担が多くなる
資産形成支援制度を導入すると、企業の人事・総務担当者には追加の事務作業が発生します。例えば、財形貯蓄を導入すれば給与システムに新たな控除項目を設定し、毎月の天引き処理と金融機関への送金を行う必要があります。
確定拠出年金を導入すれば、加入者情報の管理や拠出額の変更手続き、年に一度の運用状況通知など、法律で定められた事務処理も担わなければなりません。持株会においても、拠出金の取りまとめや株式の買付・割当、退会者対応など継続的な管理業務が発生します。
これらの事務は専門的で煩雑になることも多く、担当部署の負担増は避けられません。特に中小企業では人事・総務部門の人員が限られているため、日常業務に加えて新たな制度管理を行うことは大きな負担となるでしょう。
ミスなく運用するためには、担当者が制度の細部まで理解し正確に処理する必要があり、そのための教育やマニュアル整備も求められます。また、従業員からの問い合わせ対応(「今の積立残高はいくらか」「途中解約したいがどうすればよいか」等)に時間を割かれる場面も増えるでしょう。
このように、福利厚生として資産形成制度を提供する際には一定の事務負荷が発生することを事前に認識し、必要なら外部委託の活用やシステム化を検討することが重要です。
担当者を確保するため引き継ぎなどでコストが発生する
資産形成支援策を社内で運用していくためには、専門知識を持った担当者の存在が欠かせません。制度導入当初はベンダー(金融機関やコンサルタント)の助けを借りられるとしても、最終的な社内窓口となる担当者が必要になります。
しかし、担当者が異動・退職した場合、その役割を引き継ぐ人材を確保しなければなりません。福利厚生制度は一度導入すると長期にわたり運用が続くため、「担当者の属人化」を避ける工夫が求められます。
担当者交代の際には、新任者への引き継ぎ研修や業務マニュアルの整備などにコストが発生します。例えば、確定拠出年金の知識や最新の税制を把握するには研修参加や資格取得が必要かもしれません。
持株会の運営ルールを理解するにも専門的な知識が要ります。こうした引き継ぎが上手くいかないと、制度運営に支障が出たり従業員への案内が滞ったりするリスクもあります。
また、場合によっては外部から専門知識を持つ人材を中途採用する必要が生じるかもしれず、その際の採用コストや人件費負担も考慮しなければなりません。
資産形成支援の福利厚生を維持するためには、担当者に対する継続的な教育と組織内での知識共有が不可欠であり、それに伴うコストもしっかり見積もっておく必要があります。
福利厚生として資産形成を提供している企業の割合
大企業の定義と提供割合
「大企業」と「中小企業」の区分は文脈によって異なりますが、一般的には大企業とは事業規模の大きな企業を指し、法律上は製造業で従業員301人以上(もしくは資本金3億円超)などと定義されています。
ここでは厚生労働省の調査データに沿い、従業員数が数百人を超える規模の企業を大企業とみなします。実際、厚生労働省「就労条件総合調査」の結果によれば、従業員1,000人以上の企業の約75%が財形貯蓄制度など何らかの貯蓄支援制度を導入しています。
また、退職金や企業年金(確定拠出年金・確定給付年金)といった老後資金準備の制度を導入している大企業は90%以上にのぼります。多くの大企業では、財形貯蓄・持株会・企業型年金といった複数の制度を組み合わせ、従業員のライフステージに応じた資産形成支援を行っているのが現状です。
福利厚生が充実していることは大企業の魅力の一つであり、資産形成支援制度もその一環として広く定着しています。
参照元:就労条件総合調査|厚生労働省中小企業の定義と提供割合
中小企業は、大企業の基準に満たない企業を指し、業種によって細かい定義は異なるものの、一般に従業員数が数十~数百人規模の企業を指します。中小企業における資産形成支援制度の導入率は、大企業と比べて低い傾向があります。
前出の厚労省調査によれば、従業員30~99人の企業で財形貯蓄など貯蓄制度を導入している割合は約25%にとどまり、100~299人規模でも約44%と半数未満です。
つまり、中小企業では約半分以上の企業が資産形成支援の福利厚生を提供できていないのが実態と言えます。
しかし、これは裏を返せば中小企業にとって大きなチャンスでもあります。業界平均ではまだ珍しいこれらの制度をあえて導入することで、従業員や求職者に対して「社員思いの会社」「福利厚生が充実した会社」という強いアピールが可能になるからです。
特に若い世代の求職者は大企業志向が強い傾向にありますが、中小企業でも大企業並みの資産形成支援策があれば、「この会社なら安心して長く働けそうだ」と感じてもらえるでしょう。
また既存社員にとっても、自社で想定外に充実した制度が使えることに驚きと喜びを感じ、モチベーション向上や愛社精神の醸成につながるかもしれません。
中小企業が資産形成支援策を導入することは、人材獲得面でのPR効果が非常に大きいのです。ぜひ積極的に検討してみる価値があるでしょう。
中小企業こそ資産形成支援の福利厚生を導入し、他社との差別化を図りましょう。その際にはマネーリペアが強力なパートナーになります。
福利厚生で財形貯蓄制度などを導入する手順と方法
導入の検討
まず、どの資産形成支援制度を導入するかを社内で検討します。経営陣や人事担当者は、自社の従業員のニーズや年齢構成、企業規模、予算などを総合的に考慮して、適切な制度を選択する必要があります。
若い従業員が多いのであればまずは財形貯蓄(一般財形)から始めてみる、退職金制度が未整備であれば企業型確定拠出年金の導入を検討する、社員から住宅購入希望の声が多ければ財形住宅貯蓄を用意する、といった具合に優先順位をつけます。
制度導入にあたっては、社内規程や就業規則への明文化も視野に入れながら、労務面・法務面の要件を確認します。特に確定拠出年金は法令に沿った設計が必要であり、金融庁や厚生労働省への届出手続きも伴います。
また、制度導入によるコスト試算も重要です。例えば、企業型DCで企業拠出を行う場合、その掛金総額が人件費に与える影響を試算します。持株会で奨励金を出すなら年間でどの程度の費用になるか、社内FP相談を提供するなら委託費用がいくらか、といった具体的な数字を算出し、経営層の理解を得ます。
社内での合意形成では、制度導入のメリット(従業員満足度の向上、離職率低下など)をデータや他社事例とともに示すと効果的です。経営会議などでプレゼンテーションを行い、「なぜこの福利厚生が今必要なのか」を明確に伝えましょう。
また、既存の福利厚生との整合性(例えば、すでに退職金制度がある中でDCを導入する場合の位置づけ)も整理しておく必要があります。こうした事前検討を十分に行うことで、導入後のギャップや想定外の問題を減らすことができます。
取扱金融機関やコンサルティング先の選定
制度の方向性が決まったら、その運用を委託する金融機関やコンサルティング会社を選定します。財形貯蓄であれば銀行や信用金庫(勤労者福祉協会経由で取扱うケースもあります)が窓口となります。
各金融機関で金利や口座維持条件、オンラインサービスの有無などを比較検討しましょう。確定拠出年金の場合、信託銀行や生命保険会社、証券会社などが運営管理機関としてサービスを提供しています。
商品ラインナップ(投資信託の種類や信託報酬水準)、システムの使いやすさ(加入者がWEBで残高確認・配分変更できるか)、加入者向けサポート(コールセンターやセミナー)などを比較し、自社の社員にとって利用しやすい提供先を選びます。
社員持株会については、証券会社や信託銀行が事務局代行サービスを提供しています。株式の取引手数料や管理費用、システム上で社員が自分の持株残高を閲覧できるか、といった点を確認します。奨励金の支給を行う場合、その計算と付与を自動化できる仕組みがあると管理が楽になります。
社内FPサービスや金融教育プログラムを導入する際は、専門の会社(例えば金融教育に特化したコンサルティング企業)に相談します。
- 講師派遣型の研修
- オンラインでの学習
- 個別相談は対面かオンライン
といった提供形態も業者によって様々です。
費用体系(従業員一人当たりいくら、もしくは時間あたりいくら等)や提供できるコンテンツの幅(投資、保険、税金など網羅しているか)を確認し、自社に合ったパートナーを選びましょう。
福利厚生の専門サービスであるマネーリペアを活用すれば、制度設計から従業員向けのフォローまでワンストップでサポートを受けることも可能です。
労使協定の締結
福利厚生制度の導入に際しては、労使間の正式な合意手続きも重要です。特に給与天引きで拠出や積立を行う制度では、就業規則への明記や労使協定の締結を求められることがあります。
労働組合がある企業では、事前に制度内容を組合に説明し、同意を得るプロセスが不可欠です。組合との協議では、対象者や掛金の扱い、会社負担の有無など細部まで取り決めておき、書面に残します。
労働組合が無い場合でも、社員代表との協議が必要になるケースがあります。例えば確定拠出年金では、法律上、導入に際して従業員代表の合意を得ることが要求されています(厚生年金被保険者の過半数代表による合意)。
財形貯蓄の場合も、給与控除の実施に関する社員の同意を文書で取っておくことが望ましいでしょう。
労使協定の内容には、制度の目的、会社と従業員の拠出割合(あれば)、加入資格(正社員のみか契約社員も含むか)、積立金や掛金の上限、途中で退職・解約する場合の扱いなどを盛り込みます。
明文化することで、後々のトラブル(「聞いていなかった」「そんな約束ではなかった」等)を防ぐことができます。協定締結後は、その内容を全従業員に周知し、新しく入社した人にも就業規則や案内資料を通じて知らせるようにしましょう。
従業員への説明・募集
制度の準備が整ったら、従業員への説明会を実施します。新しい福利厚生制度は、社員にとって聞き慣れない用語や仕組みも多いため、できるだけ丁寧にわかりやすく説明することが大切です。
まず社内通知やメールで概要を知らせ、その後希望者や対象者を集めて説明会を開くと良いでしょう。可能であれば、契約した金融機関やFPサービスの担当者に来てもらい、専門的な部分も含め説明してもらうと信頼性が高まります。
説明時には、制度に加入するメリットを具体的な数字で示すと効果的です。例えば、「毎月1万円を財形貯蓄で積み立てると5年で60万円の元本が貯まり、利息が○○円つきます」「確定拠出年金に月1万円拠出すると年間で所得税・住民税が約○万円軽減されます」など、シミュレーションを用いて分かりやすく伝えます。
併せて、リスクや留意点(例えば持株会なら株価変動リスク、DCなら元本割れの可能性)についても正直に説明し、十分に理解してもらうことが重要です。
募集の際には、加入手続きの方法と期限を明確に伝えます。申込書の書き方や提出先、締切日、初回控除開始時期など、具体的なフローを示しましょう。
希望者全員から申込みが集まった後は、社内で取りまとめて金融機関等に連絡し、口座開設や初回拠出の処理を行います。また、制度開始後も定期的にフォローアップを行いましょう。
例えば、年に一度は制度の利用状況を報告したり、追加募集の案内をしたりすると、途中で関心を持った社員も参加しやすくなります。社内報や掲示板で「○○制度を利用してマイホーム購入を目指しています!」といった利用者の声を紹介するのも、制度定着に有効です。
福利厚生で資産形成ならマネーリペア
ここまで、様々な資産形成支援制度について解説してきましたが、「自社でこれらを一から用意するのは大変そうだ」と感じた経営者・人事担当の方もいるかもしれません。そのような会社様に当社では金融教育に特化した福利厚生サービス「マネーリペア」を展開しています。
マネーリペアは、株式会社インプレームが提供する法人向けプログラムで、専門のファイナンシャルプランナーが従業員の金融リテラシー向上と資産形成を包括的に支援してくれます。
マネーリペアが提供する主なサービス内容
- 金融リテラシー勉強会の開催
社内またはオンラインで定期的にお金に関する勉強会を実施します。源泉徴収票の見方や節税の基礎から、NISA・iDeCoの活用法、株式・投資信託の基礎知識まで、幅広いテーマをわかりやすく解説します。初心者向けに噛み砕いた内容なので、金融知識がゼロの社員でも安心して参加できます。
- プロのFPによる個別相談
従業員一人ひとりが抱えるお金の悩みに対し、資格を持ったファイナンシャルプランナーがマンツーマンで相談に乗ります。
結婚や出産に向けた貯蓄計画、マイホーム購入や住宅ローンのシミュレーション、保険の見直し、老後資金の計画など、人生設計に関わるあらゆる相談が可能です。
「相談したら年間の手取りが20万円増えた!」という声が出るほど、具体的な節税アドバイスや支出見直し提案など実践的な助言が得られます。
- 資産管理ツールの提供
従業員各自が自分の資産状況を一元管理できる専用システムを提供します。預貯金や証券、保険、ローンなどを入力すると、キャッシュフロー表やライフプランシミュレーションが自動で作成され、自分の将来像を視覚的に把握できます。「いつまでに何円貯めれば目標達成できるか」が一目で分かるため、日々のマネープランニングに役立ちます。
マネーリペアの導入によって、ある企業様では、「勉強会や個別相談を通じて従業員の手取り収入が増え、直近1年の離職率が低下した」という声が上がっています。
また、「税金や年金の質問が総務部に来なくなり、本業の業務に集中できるようになった」という効果も報告されています。社員の金銭的不安が解消されることで、会社への満足度やエンゲージメントが高まり、結果的に生産性向上や人材定着につながっているのです。
企業側の負担が少ないのもマネーリペアの魅力です。専門知識がなくても外部のFPがすべて対応します。
金融教育を通じた資産形成支援は、これからの時代にますます重要になる福利厚生領域です。
マネーリペアを活用して、自社の従業員が安心して豊かな人生設計を描けるよう支援してみませんか?
資料請求・無料相談のお申し込みは以下よりお気軽にどうぞ。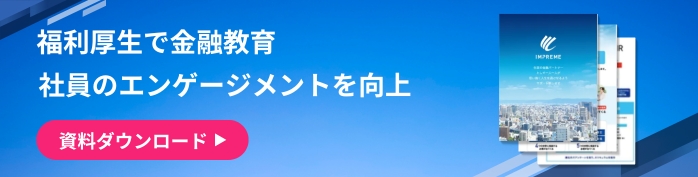
まとめ
福利厚生を通じた資産形成支援は、従業員の将来の安心と企業の持続的な発展に寄与する重要な取り組みです。
一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄といった制度から、企業型確定拠出年金、社員持株会、さらには社内FPサービスまで、多彩な手法が存在します。それぞれ仕組みやメリットは異なりますが、共通して言えるのは「従業員の経済的安定が企業への信頼と貢献意欲を高める」という点です。
中小企業においても、これらの制度を積極的に取り入れることが、優秀な人材の確保や定着率向上につながるでしょう。従業員の資産形成を支援する福利厚生は、企業から社員への「将来への投資」と言えます。
その投資はやがて、社員の高いエンゲージメントや生産性向上という形で企業に還元されます。ぜひ自社の状況に合わせて最適な制度導入を検討し、社員が安心して働ける環境づくりを進めてください。福利厚生による資産形成支援の充実が、社員と会社の双方にとって大きな財産となるはずです。

- この記事を書いた人
江本 一郎
株式会社インプレーム 代表取締役皆さまの価値観に合ったライフデザインを提供し、人生100年の時代をより豊かに過ごせるよう、お子様、お孫様へと世代を超えた金融のトータルサポートを提供していきます。
https://impreme.jp/
目次
貴社の福利厚生に新たな価値を加え、
従業員のご家族を含めた資産形成と経済力を
トータルサポートいたします。
『マネリペ』をぜひご利用ください。